
F interview 01
徳島県から問いかける環境問題。
Z世代を担う女性の
小さな町から踏み出す大きな1歩。
_edited.jpg)
上勝町 ゼロ・ウェイストセンター
大塚 桃奈
徳島県の県庁から南西方向に車で50分。豊かな緑の山々に囲まれた土地、それが徳島県上勝町である。
上勝町という人口約1500人の町で、2003年に日本で初のゼロ・ウェイスト宣言が出された。
ゴミになるものをゼロにする、という大きな目標に今もなお向かっている取り組みに影響を受けて、大塚桃奈さんは上勝町に移住した。環境型公共複合施設である『上勝町 ゼロ・ウェイストセンター』の運営で、活躍する大塚さん。
関東地方の中でも都市部にあたる神奈川県で生まれた彼女は、なぜこの小さな町にいることを決めたのか。上勝町から見える「未来」の景色を、大塚さんに聞きました。
プロフィール
大塚桃奈
Otsuka, Momona
株式会社BIG EYE COMPANYのCEO(Chief Environmental Officer)。
1997年生まれ。高校3年生のとき、ロンドン芸術大学にファッション留学する。モノがどのように作られ、捨てられるのか見つめ直すようになり、そのなかで上勝町の取り組みを知る。2020年3月に国際基督教大学教養学部卒業後、徳島県・上勝町に移住する。
現在は「上勝町ゼロ・ウェイストセンター」の運営に関わりながら、ゴミと向き合う日々を送っている。
(プロフィール写真:ヤマザキノブアキ)
上勝町との出会い
上勝町を初めて知ったのは大学生のときです。ゼロ・ウェイストセンターの建築に携わっている建築家の中村拓志さんを通じて上勝町を知りました。町内には7年前にオープンした『上勝ビール』というビールを作っている醸造施設の『RISE&WIN Brewing Co.』があり、そこの施設の建築にも中村さんが携わっていました。
学生時代、地方でのローカルな循環のあり方というものに興味を持ち始めていたので、なぜ山の中でビールを作るんだろうという興味から上勝町に訪れたことがきっかけです。
初めて上勝町に訪れた時、まずこの山の景色と暮らしに衝撃を受けました。私は神奈川県出身なのですが、海の近くに暮らし、アクセスのいいところに住んでいたのでまったく暮らしの景色やあり方が違う。日本の中でもいろいろあるということを知りました。
上勝町は標高100~700mの間に55の集落が点在しているので、車がないと非常に不便な町です。ですから、移動の時間や生活の時間の流れも違うと感じました。最初に宿泊した場所は農家民宿でしたが、とても優しくしていただいて、人の温かみというか、同じ目線で関わってくださっている感覚がありました。
2003年と2020年に出されたゼロ・ウェイスト宣言の違いについて
もともと、2003年に発表されたゼロ・ウェイスト宣言は、上勝町のゴミ処理においてのピンチが積み重なっている中で変わらなければいけないと取り組み続けた意識の中で、出たものでした。この宣言には、2020年までに地域で処理が不可能な焼却・埋め立てゴミをなるべくゼロに近づけよう、そのための仲間づくりを行っていこうということが書かれていました。
2020年を迎えるにあたり、リサイクル率は8割を超えましたが、地域の中でゴミになる物をゼロにすることは達成できていませんでした。この上勝という四国で一番小さな町の中では、焼却・埋め立てになってしまうものが、まだまだ出ています。
それはどこから来ているものなのかというと、上勝町の外から来ていて、誰が作っているのかというと、企業がデザインして販売をしている。つまり、その流れを生活者が選んでいる行動を変えていかないといけないんです。目標としていた2020年にもう一度宣言をすることで町としても無理せずに、住民の豊かさを求めて取り組み続けようということに加えて、企業連携や環境教育にも力を入れていこうと考えています。

▶2003年と2020年に発表された 宣言の比較表。
私自身は、2020年に上勝町に移住をしていて、この新しいゼロ・ウェイスト宣言文のディスカッションにオブザーバーとして参加していましたが、メインでこの宣言の内容を考えていたのは上勝町役場と町のゼロ・ウェイスト推進員の方です。
2020年のゼロ・ウェイスト宣言はさらにアップデートしたという形になると思います。
宣言は3つの大きな柱からできています。ひとつめに、ゼロ・ウェイストの選択肢によって住民一人ひとりが豊かな気持ちになれるようにすること。
ふたつめは企業連携です。異業種の連携を上勝町から作ることでゴミになるものをゼロに近づけていくこと。
最後に、地域内外にゼロ・ウェイストに取り組む人材をつくることです。この3つのポイントが推進員の方や役場の方の話し合いによってクリアになり、宣言に繋がりました。

▶2020年に掲げられた3つの柱。
日本でゼロ・ウェイストの活動を行っている5つの自治体について
ゼロ・ウェイストの活動を行っている自治体は上勝町の他にも福島県みやま市と大木町、奈良県斑鳩町、熊本県水俣町があります。5つの自治体が活動をしていますが、個人的にはもっと全国的に広がり、仲間が増えたらいいという思いがあります。
この5つの自治体はどこも、焼却施設の老朽化や寿命、埋め立ての容量の限界を迎える中でオルタナティブチョイスとしてゼロ・ウェイスト宣言を掲げました。
ピンチを迎えた自治体がやることではなくて、社会全体としてゴミとなるものをなくすという意識をつくることが大切だと思います。
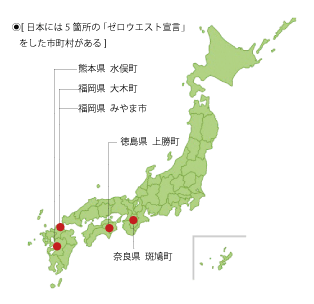
▶「ゼロ・ウェイスト」を掲げる日本全国でわずか5つ。
数多くある自治体の中で5つと考えると、まだまだ少ない数字だ。
ゼロ・ウェイストセンターの取り組みについて
ゼロ・ウェイストセンターには、上勝町民が利用する中間処理施設「ゴミステーション」に加え、リユース拠点である「くるくるショップ」、交流ホール、オフィススペース、そして体験宿泊施設である「HOTEL WHY」が併設しています。ホテルではゼロ・ウェイストアクションとうたい、体験を大切にしています。
チェックイン時に、石鹸は必要な分量だけ切り分けたり、コーヒーやお茶を量り分けたりして、「どのくらいの量が必要か」という問いかけから始まります。そこから施設を見学して、最後は滞在中に出したゴミを、自身がゴミステーションで分別します。

▶リユース拠点の「くるくるショップ」。
この写真の中だけでも、多くの食器類や衣類が確認できる。
(写真:Transit General Office Inc. SATOSHI MATSUO)
2021年は、センター内にあるホテルの利用者が1500人以上、日帰りで見学された方を含めると5000人の方がいらっしゃいました。上勝町の人口より多くの方が訪れている状況です。
先日は、ポーランドから来日したお客様がいました。廃棄物マネジメントについて研究をされている教授の方で、日本の事例を見たいと上勝町に来ていただき ました。
他にも、メーカー企業の方が1泊2日で施設にいらっしゃいましたが、センターの見学やゴミステーションでの分解作業を通して、作る側の責任というものを実感したと仰っていました。
夏休みや連休になると、家族で利用されるお客様がいらっしゃいます。特にお子様に多い感想なのですが、生ゴミをコンポストに入れて土に還すという行為がすごく衝撃的で印象に残る方が多いようです。こうして手で触れていただくことでより循環を実感していただくきっかけになっていると思います。

▶ホテルの室内からは山々に囲まれた自然豊かな景色を一望できる。
(写真:Transit General Office Inc. SATOSHI MATSUO)
施設で働いている私たちスタッフもまだまだ、ゼロ・ウェイストとはなにか、一人ひとり考えていますし、上勝町自体も正解がない中でなにがベストなのか考えている最中です。利用される方だけでなく、私たちも学びながら問いを持ち続けたいです。
大塚様の考える、ゴミ問題への向き合い方
ゴミ問題というものは複雑で難しい問題です。だからこそ、自分ができるところから行動をするようにしています。
例えば、出張などで出かけるときはマイカトラリーを持って出かけたり、レストランで提供される使い捨てのお手拭きは使わずにお手洗いで手を洗ったりしています。ちょっとしたことではありますが、一緒にいる人や店員の方とのコミュニケーションにも繋がることがあります。
これは私の学生時代の経験も影響しています。大学2年生のとき、再生エネルギーがほぼ100%であるコスタリカに留学に行きました。コスタリカ環境工学の講師 が徹底的に脱プラを行っている方でした。フィールドワークで出かけた先のレストランで、フライドポテトのケチャップがプラ容器に入っていたら
「それは使いませんので、お店のケチャップを器に直接出してください」
と言うような方で、そこでコミュニケーションが生まれ たこともありました。
過激な考え方だと思う方もいるかもしれないですが、プラスチックを使うことを完全に否定しているわけではなくて、自分なりにできることをする、という工夫もできるという示唆にもみえて、面白いと思いました。
私もまだ完璧ではないので、できるところから。あとは、なるべく作っている人の顔が見えるものや、自分が共感したり、愛着を持てたりするようなものを選ぶようにもしています。
もちろん、皆さんでも普段の生活から環境に対してできることはいろいろありますし、人によってそれぞれの方法があると思います。
私自身は、上勝町の取り組みを知って、ゼロ・ウェイストという言葉に触れたときに「ゴミの発生抑制」という言葉の意味もありますが、それとは別に「社会の中で見えなくなっている繋がりに対して思いをはせる」という側面もあると感じました。それがゼロ・ウェイストを考えるきっかけにもなると思います。
ですから、例えば環境に関心のある方であれば上勝町に旅に来ていただくことも自分が何気なく思っていたゴミについて考えるヒントになります。また自分が過ごしている間に出たゴミはどこに行くのか、自治体のゴミが回収されてどこに行っているのかということをリサーチするだけでも見方も変わると思います。
ただ、何よりも大切なのは自然の中に身を置くことだと感じています。今この、慌ただしく過ごす中で時間を詰めてしまう人も多いですが、自然の風を感じたり土に触れたりするだけでも、感覚は変わってくるように思います。

▶施設周辺は緑が囲んでいる。この広大な環境を残していくために
私たちにできることを、この自然は考えさせてくれる。
(写真:Transit General Office Inc. SATOSHI MATSUO)